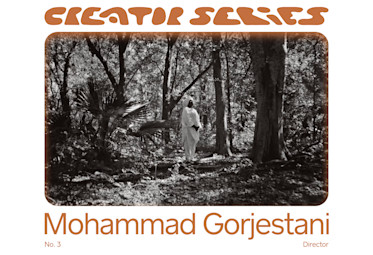今回のクリエイターシリーズでは、ベイエリア在住の映像制作者Mohammad Gorjestaniにお話を伺いました。彼はSquareの「For Every Dream」シリーズでディレクターを務め、「Yassin Falafel」、「Made in Iowa」、「Lakota in America」、「Sister Hearts」、「Exit 12: Moved by War」などのストーリー(すべて英語のみ)を手掛けてきました。逆境にあるアメリカを背景として起業することの意味を、ありのままにそして感動的に描いたこれらの作品は、大きな反響を呼びました。
このクリエイターシリーズでは、これまで世界トップクラスのクリエイティブパートナーやコラボレーターをお招きし、創作活動についてインタビューを行ってきました。今回は、Mohammad Gorjestaniと、グローバルブランドグループ・クリエイティブディレクターであるEileen Tjanの二人を迎え、映像制作者としてGorjestaniが歩んできた道のりについて語ってもらいました。撮影クルーはもちろん、撮影の被写体となる人々など、創作活動に一緒に取り組むすべての人にとって、これまでのアーティストとしての経験がどのような支えになっているのか、詳しくお聞きしました。

Mohammadさん、お越しいただきありがとうございます。まずは自己紹介からお願いします。
自分の職業は、今のところビジュアルストーリーテラー兼アーティスト、といったところです。映像という媒体で仕事をすることがすごく好きですが、他にも、写真撮影やクリエイティブ・ディレクターとしての活動にも携わっています。また、クリエイティブスタジオでありプロダクション会社であるEVEN/ODDのパートナー兼創立者でもあります。
僕の母だったら、僕についてどんなふうに紹介するか考え、生まれたころの話を少ししてみたいと思います。出生地はイランです。ちょうど革命後だったのですが、両親は労働者階級のアーティストとしてイランに留まり、イラン国内でできることを模索していました。しかしイラン・イラク戦争が勃発し、私たちが住んでいたテヘランが空爆されたため、亡命することになりました。まずはトルコへと逃れ、1年ほど狭い1部屋で家族みんなで暮らしました。その間父が何度もドバイの米国大使館へと足を運び、ビザの申請をしてくれました。ようやくビザが給付され、カリフォルニア州サンノゼに移住しました。
移住後は、シリコンバレーのすぐそばにあるサンノゼ西部のセクション8(米国政府主導の住宅サポートプログラムが実施されている地域)に住み、いろいろな国から移民が集まるコミュニティで育ちました。そんな環境で暮らす中で、世界に対する考え方や、アメリカという国に対するイメージを自分の中で身に付けていきました。
子どものころの印象的な思い出はありますか。ぜひ聞いてほしいと思うような話は?
子どものころの話は、ありきたりでつまらないかもしれません。そのころは、何かに関心を持つということ自体あまりなかったのですが、そんな私の興味をとても惹いたのは「Goosebumps」という物語でした。プロットやストーリーのコンセプトに夢中になり、どうすれば自分でもストーリーを書けるのか考えるきっかけにもなりました。3年生のときの先生に、課題の「つまらない」本じゃなくて怖いストーリーを読みたいと言ったら、この本を紹介してくれたのです。ページを進めるたびに先が読めなくてドキドキして、異世界に迷い込んだような気分になったのを憶えています。
今思うと、この本にこれほどまでに惹かれたのは、アメリカの郊外を舞台にストーリーが描かれていたからではないかと思います。自分が育った場所から目と鼻の先のところで起こっている話なのに、住んでいる狭いアパートや暮らしからは手が届かない遠い世界の話のようにも感じました。身近な場所で起きているストーリーに、この本は私を引き込んでくれたのです。
映像制作に興味を持つようになったのは、「To Kill a Mockingbird(アラバマ物語)」のおかげです。高校1年のときにこの小説を読んで、いい作品だと印象に残りました。だけどもっと衝撃を受けたのは映画を観たとき。この映画がきっかけで、書かれた文章を映像化することについて、実際に興味を持ちはじめました。本を読むたびに、映像化された作品を早く見てみたいと思うようになりました。本と映画を比較することに情熱を感じ、本を映像化するときにどんなアレンジが加えられているのか探したり、自分なりに批評したり分析したりしていました。
その経験がきっかけで、「ストーリーの紡ぎ手になりたい」という気持ちが強まったんでしょうか?
本格的に映像制作の技巧についてもっと知りたいと思うようになったのは、Abbas Kiarostamiの「Taste of Cherry」を観たときでした。私は18歳で、両親のイラン旅行に一緒に行けなかったことを覚えています。当時私はレスリングの奨学金を目指していて、自宅でトレーニングに励まなければなりませんでした。これまでに経験したことのない、ホームシックのような寂しい気持ちになっていましたが、この作品を観ると、寂しい気持ちが癒されたんです。なんとも懐かしい場所に戻ったような感覚でした。人生の最初の5年間はイランで過ごしていたからかもしれません。「どうしてこんな気持ちになるんだろう?なぜ自分はこの作品のことを考え続けているのか?一体どんなふうにこんな映画を撮れたんだろう?」そんな疑問を冷静に考え続けたのを憶えています。
この作品に出会ってから、私自身も初めて、物語やアイデアに考えを巡らせるようになりました。イメージやプロットを一つずつ順番に繋げて、より壮大なメッセージや雰囲気を生み出したいという気持ちが強まっていきました。アメリカの特定の階級で育つと、クリエイティブな職業に就きたいなんて考えもしない子どもたちが沢山います。私自身も両親の経験を見てきました。イランではアーティストだった2人が、アメリカで生活していくためにはアーティストとしての活動を諦めざるを得なかったのです。
Lakota in Americaからのワンシーン
それでもなおクリエイティブな世界を追求しようと思うようになったきっかけは?
これについては、私自身もこれまでに何度も考えました。それでも、やはり行きつく答えは、「両親にアーティストとしてすばらしい才能があった」ということでした。つまらない答えに聞こえるかもしれませんが、私がクリエィティブな世界に進んだ理由は、「両親の血」を受け継いだからだと思います。私の中には、私の意思とは関係なく、アーティストとしての力が備わっていて、とにかく自然の流れに身を任せるしかない。あるときからそう思うようになりました。
移民一世や海外移民の子どもの多くが、新しい環境で両親がどうにか生き抜こうと懸命に励む姿を間近に見て育ちます。親が新しい文化に同化しようと努力するのを見て、自分も同化するのです。それでもやはり成長するにつれて、自身の文化を振り返り、自分のアイデンティティや国籍との関係、亡命せざるを得なかった歴史や出来事などについて考えだすようになります。まるで自分の内側に懐中電灯で光を当てるように、もっと調べたい、もっと知りたいと思うことを見つけていきます。そんなふうに自分の内側を探るプロセスで「何か」を見つけ、その何かのカタチを変えたり、型に入れたりして模索を続け、納得できるような状態になるまで追求していきました。
その模索が、映像制作に繋がったのはいつごろですか?
当時ちょうど大学に進学して、夏休みはレスリング部の練習に明け暮れていました。その途中でケガをしたのです。肩の腱板損傷。その年だけでもう4回目でした。とうとう辞めるときがきたのかと落ち込み、ただぼーっと座ってずっと映画ばかり見ていました。「シティ・オブ・ゴッド」、「セブン」、「ブロウ」など、どれも映画史に残る傑作です。その後、大学の短期コースに通い始めて映像の授業をいくつか取りました。単位を取るのも楽な授業だと噂で聞いていましたし、映画を見るのも好きでしたから。「いいんじゃない、暗い部屋に集まって、映画を見て、一服吸ってから授業に出て、成り行きに任せればいいか」という感じでした。そんなふうに気軽に受講したこの授業で、本物のシネマに触れることになりました。「科学のようになんて体系的なんだ。それに実践的だ」と驚きました。完全に引き込まれましたが、まだ本当の魅力は理解していませんでした。
ある課題で、ストーリーのあらすじを書くことになりました。実際に提出したものの出来栄えは、個人的にそれほど良くないと思っていたのですが、先生はすごくほめてくだいました。「これはすごくいい。素質を伸ばすために、映画学校に進学してみてはどうか」と勧められました。当時授業がないときはゴルフ場で働き、皿洗いのバイトもかけ持つような生活だったので、「映画学校!?そんなところに通っている人は誰一人知らないんだけど」と、まるで他人事みたいな感じでした。
その先生と一緒に調べてみたものの、南カリフォルニア大学やニューヨーク大学などの有名大学は、私が工面できる学費をはるかに超えていたので、最終的には学生ローンと高校時代から働いて貯めてきたお金で、バンクーバーの1年間のプログラムを受講することにしました。このプログラムで私にとって初の映像作品を作りました。とても個人的な思いが詰まった作品に仕上がりました。
バンクーバーで過ごすうちに、私は多くの束縛から解き放たれていきました。もう出身地がどこであるかで自分を定義する必要がなくなったからです。そして同時に、自分が思う以上に自分のアイデンティティを深く掘り下げることができました。すると自分の中に「繊細で壊れやすいもの」がたくさん存在していることに気が付きました。また、移民として異国に住まなければならなかった過去や、自分が育った環境が、どれだけ自分に影響を及ぼしたかも再認識しました。このとき初めて、本当の意味で自分の棚卸しを始めることができたのです。とにかく、ほぼ無意識のうちにストーリーを書き、脚本も作り、映像に仕上げたものがトライベッカ映画祭で上映されました。
2006年のこの映画祭では、参加者のうち私が最年少の映像制作者で、それまではニューヨークに行ったことなど一度もありませんでした。だけど自分が作ったものが表彰され、仕事にすることができるかもしれないと、初めて実感することができました。それに、とても個人的な感情に向き合ったことが、実際に自分にとって実り多い経験につながったのです。世の中では、私の育った社会経済的な環境だけを見て、「こうあるべき」という期待を私という存在に求めてきます。しかし、自分の感情に向き合ったことで、このような期待や、自分自身が作り上げた固定概念に縛られるのはやめようという自信を得たことが、自分にとってはとても重要な意味を持ちました。
もちろん、物事がそれほどにスムーズに進んだわけではないのです。映画祭に参加したその年にサンフランシスコへと引っ越しましたが、何年もレストランで働きながら貯金と時間のやりくりの毎日。助成金に応募するために、自分のアイデアをまとめて申請書を何枚も書きました。どうしようもない駄作もたくさん作りましたし、テーマが定まらず何が言いたいかわからない作品もありましたが、とにかく創作を続け、行動し続けたことは褒め称えたいと思います。
アーティストであるためには、出来の悪い作品は手放していかなければなりません。異論もあるかもしれませんが、創造力を成長させるための自然な過程だと私自身は強く信じています。
当時を振り返ると、「どうすれば、今後はこうしなくて済むか」を学ぶために必要な時間だったと思っています。
ただ映像制作に、特にディレクターとして携わっているときは、「自分の役割はアーティストだけだ」なんて考えるのは馬鹿げていると思います。ディレクターはクリエイティブな役割であるのはもちろんですが、それと同時に、リーダーシップが求められます。映像制作にはいろいろな人々との共同作業が欠かせません。ディレクターの仕事で肝心なことは、周りの人々の力を最大限に引き出すこと。彼らをサポートして内に秘めた可能性を発揮してもらうこと。そして厳しい状況でもプロジェクトを先に進めて同じ方向に向かって舵を切ることです。
創作活動をする中で、どのようにインスピレーションを維持していますか?また、日々さまざまな作業に携わる際、どんなふうに創造力を取り入れていますか?
私には、決まったルーティーンや習慣がたくさんあります。創造力を発揮するための練習のようなものです。「OK、映像を見る時間だ、今度は映像の見直しをする時間、フォトグラファーを呼んで彼らの仕事を精査する時間」という感じです。私の場合は、ランニングしている間にクリエイティブなアイデアが生まれるのです。走っている間は周りのものが目に入らなくなり、最も深い瞑想状態に入れるからです。「責任」や「期待」などから自分自身を解放するためのスイッチのような、そしてクリエイティブに世界を味わうことができるような「日々の習慣」を持つことは大切です。自分自身の活性化やインスピレーションの源のようなものだと思うのです。
また、企業やブランドとの仕事にはどのようにして参加することになったのかと、よく聞かれるのですが私の答えはいつも同じです。自分個人の仕事に集中して、作品を仕上げること。自分が大切にしていることに対する強い信念を、ただ一心に持ち続けること。そして目の前にチャンスが訪れたり、自分で好機を開拓したりすることができれば、自分の信念をその機会につなげるだけなのです。自分自身や自分の創作したものに強い信念を持って懸命に取り組み、それがこれまで失敗につながったことはないので、皆さんにもぜひこの方法をおすすめしたいと思います。もちろんこれにも大切なポイントがあります。「長期戦になってもいい」という姿勢を持つこと、そして紆余曲折、浮き沈みがあって当然だと捉えることです。誰だって損をしたくはないだろうし、クリエイティブな仕事をしている場合はなおさら、苦境を経験をするのは容易ではないはずです。だからこそ、その乗り越え方を学ぶことが大切です。そんな姿勢や考え方を身に付けることができれば、いずれ必ず「大切な何か」を手に入れることができるはずです。
仕事を引き受けるうえで重視していることとは?Squareの「For Every Dream」シリーズではディレクターとして活躍されましたが、そもそも何が決め手でこのプロジェクトを引き受けることに決めたのですか?
「For Every Dream」シリーズは、私の創作活動にとっても、スタジオとしてのEVEN/ODDにとっても、そしてもちろんSquareにとっても、重要なターニングポイントになったと思います。今回も、個人的な思いに溢れた作品に仕上がりました。私の作品はいつも階級、文化、移民の交わりがテーマです。それは基本的に自分のアイデンティティや成長を形づくったすべてなのです。Dreamsシリーズを引き受けることに決めたのは、以前「The Boombox Collection」というシリーズを制作した経験がきっかけです。これは、これまでに自分が影響を受けた労働者階級のヒップホップアーティストを取り上げたビジュアルドキュメンタリーでした。歳を重ねたミュージシャンとしての彼らの生き様に興味があったのと、根底に流れるものが、クリエイティブな業界を生き抜く起業家精神のストーリーに通じるものがあるような気がしたのです。Boots Rileyと、今は亡きZion Iと映像作品を作りました。そして [後のSquareグローバルクリエイティブ主任の] Justin Lomax、ベイエリアのラップ文化のレジェンド的存在の彼が、僕の作品を観てくれたのです。
Justinと [グループクリエイティブディレクターである] Sean Conroy、そしてクリエイティブチームとやり取りをする中で、彼らの在り方について2つ、とても重要な発見がありました。1つは、自分たちが大切だと感じていることは、本当に大切なものとして配慮を惜しまず、また私やEVEN/ODDにとって大切なことにも寄り添ってくれたこと。2つ目は、自分の勤めている企業を心から信じているということ。しかもそれだけにとどまらず、これまでに出会ったSquareの製品を使っているビジネスオーナーのことも誠実に信じているということ。これは私にとって、とても重要なポイントでした。単なる仕事ではなく、ビジネスオーナーを大切な個人として捉えているということ。Squareを使うビジネスについて彼らが熱心に話をする様子を見ていると、自然と「このチームを信じよう」という気持ちになりました。そして、そんなビジネスが存在するコミュニティに実際に目を向けてみると、さまざまなストーリーがあちこちに溢れていたのです。
彼らの在り方こそが、嘘偽りのない誠実な映像作品を作るために欠かせない基盤なのです。その理由は明快。JustinとSeanが、大切なことを、大切なこととしてどんなときでも尊重してくれたからです。そしてこれまでに参加したどんなブランドのプロジェクトよりもじっくり時間をかけました。作品が完成してからその出来栄えを褒め称えるのは誰にでもできます。だけど、実際に現場でいろいろなことが起きている間、リアルタイムでさまざまな意思決定をしなければいけないというのは、本当に大変なことです。この作品が失敗に終わる可能性はあちこちであったにもかかわらず、彼らの信念が、「失敗するという可能性」を絶対に受け入れなかったからこそ、素晴らしい作品を作り上げることができたのです。
それにDreamシリーズの作品は、トランプが大統領に選出されて、アメリカが世界の目にさらされていた時期に作られたので、なおさら時代を象徴する作品としてその存在が際立ったのだと思います。さまざまな文化や対話の場にいやな雰囲気が流れ始めていたその時代に対して、この作品を通してちょっとした反抗をしたような感じ。振り返ってみると、やはり大胆なプロジェクトでした。社会の主流に媚びを売らず、「自分の在り方」をこんなふうに主張するキャンペーンは今まで存在しませんでしたから。
Yassin Falafelからのワンシーン
そして映像を制作する過程、特に「企業の宣伝」を目的としていた点もすごく新鮮でした。映像作品になるにふさわしいパワフルなストーリーがあって、そのストーリーを映像作品に仕上げる作り手に私を選んでくれた。こんな縁があったのは、本当にSquareのおかげです。Dreamsシリーズを代表する作品を観てみると、このユニークな制作過程を感じていただけると思います。「誰もが経済活動に参加できるようサポートする」というSquareが掲げる企業キャンペーンとしてのみ存在するのではなく、映像業界や文化面でも批判精神に富んだ存在として一石を投じたと思うのです。初のブランド名を冠した作品「Exit 12」は、アカデミー賞予選のフィルムフェスティバル(SXSW)で入賞し、Fox Searchlightの大手スタジオが上映権を獲得するまでに至りました。
シリア難民からアイオワ州の工場街の話まで、どれも一見まったく種類が異なる作品に感じるかもしれません。しかし、すべての作品が一つになって、私たちにいろいろなことを教えてくれます。「アメリカンドリーム」というコンセプトは一体何を意味するのか?私たちが日々の暮らしを送っているこのシステムの在り方とはどういったものなのか?どのような仕組みで、誰のために機能しているのか?こういった疑問にあらゆる側面から切り込んでいるのです。
このような経済的に困難な状況に陥ると、金銭的に打撃を受けるだけでなく、人々の暮らし、愛着のある場所、文化すらも脅かされるのです。
作品では感情を前面に出していると思うのですが、このプロジェクトに携わる中で、困難にぶつかるような経験をしたことは?打ちのめされるような出来事はありませんでしたか?
私が撮影前に十分に気を付けていること、それは精神面を万全の状態にすることです。しっかり準備してプロジェクトに取り掛かり、しなければならないことを実行する、それだけに集中します。難しい題材を扱うときには、ある種の感情に区切りをつけやすくするために、気持ちのスイッチのオン・オフを切り替えなければならないこともあります。撮影している題材については、自分自身が感情的になるということは許されません。感情に流されると、行うべき仕事ができなくなってしまうからです。とにかく撮影現場のエネルギーに集中するようにしています。作品を編集して作り上げるのに必要な映像を撮ることだけを考えます。撮影に没頭しているときは、感情的になる時間や余裕は自然となくなります。
そして個人的には、撮影する被写体を「コラボレーター」として捉えながら撮影に臨みます。彼らの持つ価値を彼ら自身が理解できるよう働きかけ、関係を築き上げる中で信頼が生まれます。「これまで他の誰にも話したことがなかった体験を、この場で伝えた」と言われることは、実はよくあるのです。そんなふうに信頼してもらえることは、同時に彼らに対して自分も責任を果たさなければならないということでもある。彼らと同じように、自分も誠意をもって撮影に臨むのが絶対条件ですから。感情的になって、自分の力を出し切れないなんて絶対に許されません。何があっても絶対にいいものに仕上げるんだ、そんな気持ちになるのです。
作品にぴったりのコラボレーターは、どのようにして見つけるのですか?
フィーリングの問題と片付けたくはないのですが、実際やはりピンとくるものがあるかで判断しています。誰と波長が合うか、誰の波長が自分の波長と交わってコラボレーションに役立つかは、割とすぐに分かります。絶対条件は、プロジェクトで伝えるべきメッセージに沿っていること。特に「企業の宣伝」を目的としている映像制作の場合、どこかの企業のために腹を割って話してくれる生身の人間を撮っていますので、これは絶対に譲れません。メディアは、それを目にする人々の行動に大きな影響を与えると思っています。だからこそ、この作品に取り組むときは真剣勝負です。メッセージに沿っていないと思うものがあれば、絶対に妥協しません。等身大の姿をさらけ出してくれる人がいるなら、自分も誠意をもって撮影し、彼らの視点を常に意識しながらプロジェクトに取り組みます。この人たちのありのままの魅力を、きちんと表現できているだろうか?ストーリーの中で生き生きと活躍させることができるだろうか?社会の多数派に媚びを売るだけになってしまわないか?そんなことを常に意識しなが撮影に臨んでいます。
だた綺麗な映像を撮るだけの仕事には、あまり興味がありません。私たちは、映像が伝える内容やどのように構成されているかということよりも、見映えを重視する風潮に流されているのではないかと感じています。
サンフランシスコで、ここ10年で誕生した多種多様な新しい企業を取材しましたが、ある種の文化やトレンドがあるように感じます。以前は、企業は何よりも先に、どんな商品・サービスを販売しているのかを顧客に説明することが必要でした。ブランドとしてのあるべき姿や、目指すべきアイデアの確立は、その後の話だったのです。ですがサンフランシスコの企業は技術的に優れているので、何よりも先に「実用性」や「機能性」を追求するというアイデアを確立しています。これは製品作りにおいても、実に理にかなっています。UXやUIはシンプルで親しみやすいものであるべきですから。でも個人的には、こういった原則はアートに当てはまらないと思っています。
アートでは、乱雑で、不完全で、感情的であることが許されるべきです。時にミニマルを追求するアートも存在しますが、誇張することがアートである場合もあるのです。美しさをアピールすることも、同時に醜さを意図的に前面に押し出すこともあります。不快な気分を引き起こすものも、幸せな気分を溢れさせるものも、これらすべてがアートなのです。
Sister Heartsからのワンシーン
このようなストーリーを発信することで、視聴者とのつながりを深めることを目指す企業はほかにも存在すると思うのですが、こういった企業に対して、何かメッセージはありますか?
こういったことを、単にデータポイントとして考えていたり、「多様性」や「一体性」などのテーマばかりを先行させて、「多文化マーケティング」として展開したりし、何かの「説明責任」に駆られてこのような取り組みをするのであれば、まだその真の価値を理解しきれていないと思います。真の価値とは、生身の体験をした人や、自分が懸命に取り組んでいることに同じように情熱を注いでくれる人々と、一人でも多く一緒にプロジェクトに取り組むことで、プロジェクト自体がより豊かで実り多くなり、より実態のあるプロジェクトに成長していくということです。
ストーリーで取り上げる内容について考えてみると、George Floydの一件があった後、BLM運動が社会問題化したこの時代には、個人的に少し違和感を感じています。「象徴的な変化」を求める声がどんどん高まって、本来必要な「構造的な変化」を求める声と混同されてしまった気がします。変化を起こそうとする当初の勢いもなくなってきています。多くの企業が騒動に合わせてさまざまな対応をしましたが、業績を維持し、時代の流れに合わせて必死に認識を変えようとしていた企業が、危機感に煽られて行った一種のアピールのようなものではないかと感じます。
このような状況では、パートナーシップやコラボレーションに誠実な思いがあるのか判断するのがさらに難しくなってしまいます。ここでもやはり重要なのは、相手の見極め方。誰をパートナーとするのか、プロジェクト関係者の情熱をさらに高める相手はどんな人物か?これまでのやりとりを振り返って、慎重に検討する必要があります。世論に求められ収益アップにつなげたいから、このような取り組みをしようとしているのではないか?慎重にならざるを得ません。いずれにせよ昨年を振り返ってみると、これまで無視されがちだった自分の気持ちを表す言葉や表現が、数多く注目を浴びたのが印象的です。
クリエイティブなコンテンツに携わるものとして、また特にマイノリティーのクリエイターとして、自分たちに関する誤った情報を、システムに刷り込まれることは何があっても阻止しなければなりません。自分たちの体験が持つ価値を誰よりも理解できるのは、自分たちのはずだからです。
私たちの考えに共感できる人がいれば自然と私たちのもとに寄り添ってくれるはず。自分の考えを置き去りにしてまで相手の理想に寄り添う必要はありません。これまでも自分たち独自の創作活動に取り組んできて、今後も同じように自分らしい取り組みを続けるだけです。私たちにとっての理想のパートナーは、自分の社会的地位を守るために「型にはまろうとする」のではなく、「型を作っていくこと」に関心がある人物です。この姿勢を崩すことなく、長い目で取り組みを続けていれば、自然と変化が起こり、いずれは真の進歩を経験できるはずです。
実は、「EVEN/ODD」という名前もこの考えが由来なのです。マイノリティーや差別を受けたことのある人間として、私たちが多様性や一体性について語る場合は、啓発月間とか社会改善案だけにとどまらないでほしいのです。これは決してもっとサポートしてほしい、えこひいきしてほしいというような意味ではありません。ただ他の人と同じように、経済的、文化的、創造的な能力を身に付けられるようになりたい、「Even Odds(五分五分/対等)」な関係を望んでいるだけなんです。だからこそ、こういった要因が重要な意味を持つのです。平等な社会を実現するには、一般的に求められるチェック項目を満たすだけではなく、実際に誰もが平等に能力や影響力を持てることを目指すことこそが求められているのです。